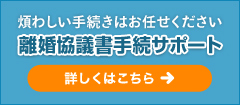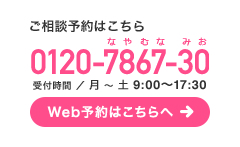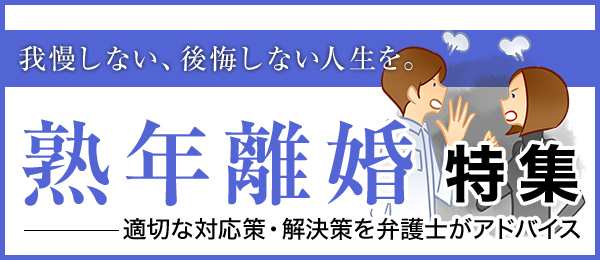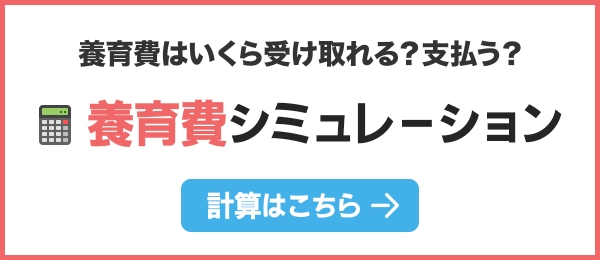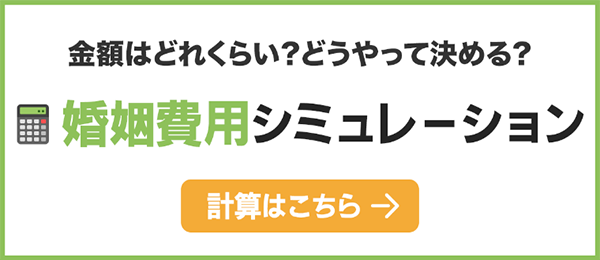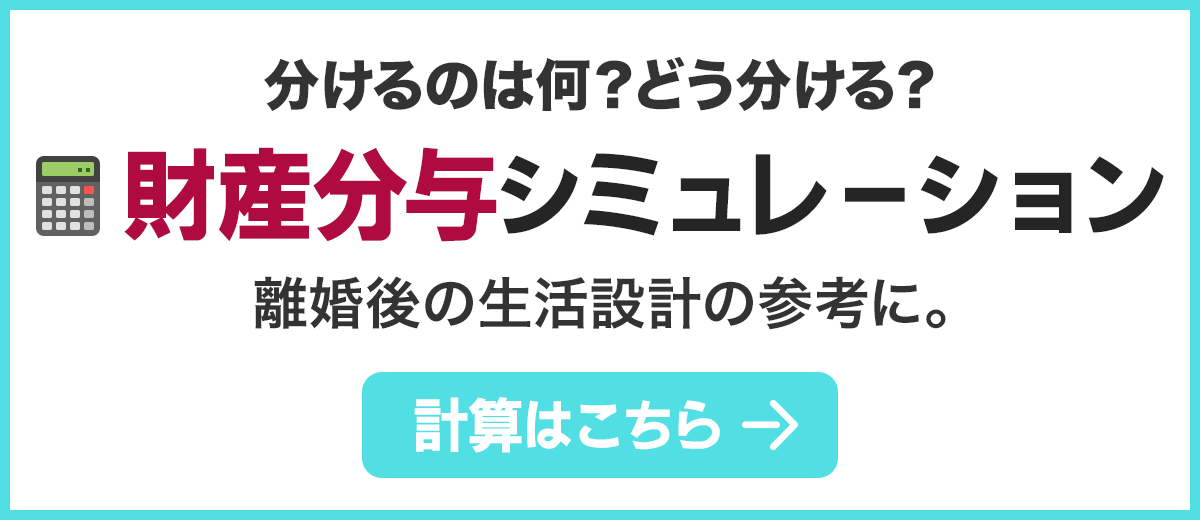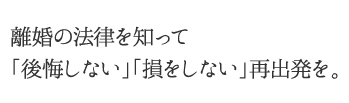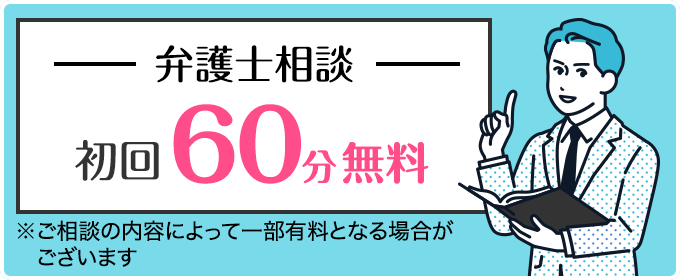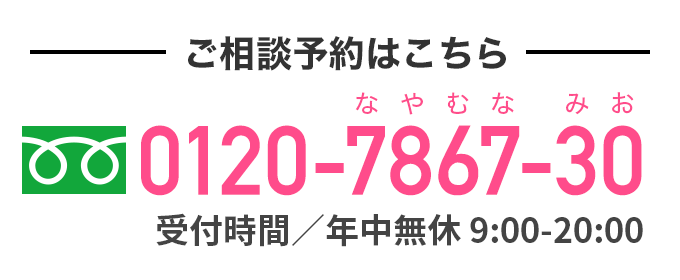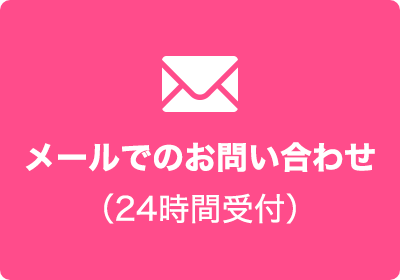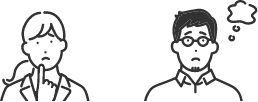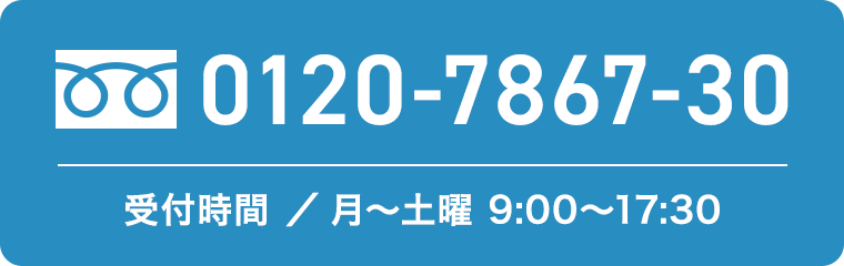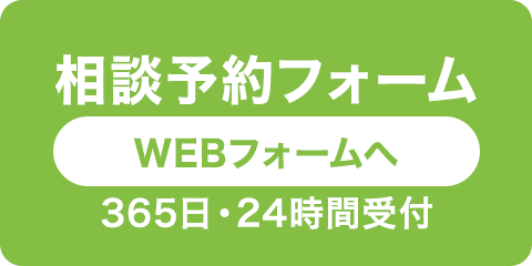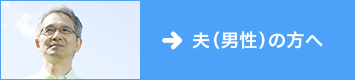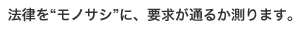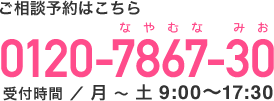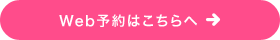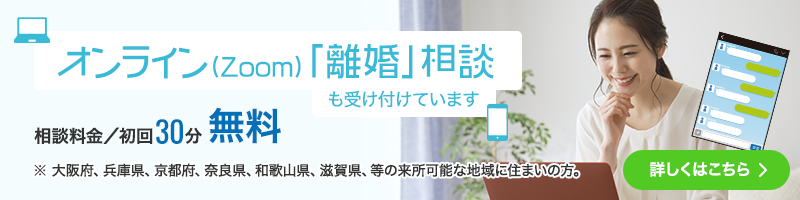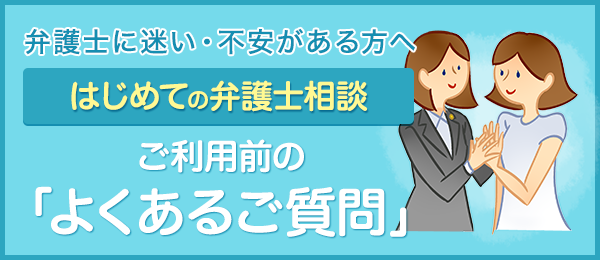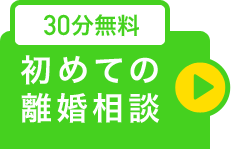離婚の手続き
離婚の手続き
調停離婚の手続きと流れ

2人で結論を出したかったけれど、堂々巡りでギブアップ!
お二人の間で離婚の話し合いに決着がつかず、協議離婚ができない場合、まずは家庭裁判所に「調停」を申し立て、離婚の話し合いを進めてもらうことになります。裁判のように形式ばらず気軽に相談でき、第三者が間に入ることで、比較的冷静に話し合いが進められます。
まず調停を。いきなり裁判!はできません |
日本では、離婚訴訟を起こす前に必ず、家庭裁判所に「家事調停」を申し立てることが法律で定められています。夫婦や親子・親族間のもめ事は、“証拠”や“法律”といったもので結論を出せることではない場合が多いから、というのがその理由です。
そこで、まず
1.「調停」という手続きを利用し、調停委員会に間に入ってもらって話し合いをする。
それでも解決しなかったら、次の手段として
2.家庭裁判所に「離婚訴訟」を起こす。
という制度になっています。これを「調停前置主義」と言います。
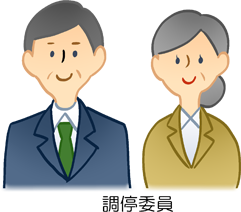
申立理由に決まりはあるの? |
理由についての決まりはありません。お二人での話し合いがうまくいかず、困ってしまって相談に行くのですから、むずかしく考える必要はありません。
例えば、
- ・「夫婦仲がなんとなくうまくいかないが、やり直したい」、あるいは「相手がどう思っているのか知りたい」といった場合は、夫婦関係調整調停(円満)として受け付けてもらえます。
- ・親権、養育費、慰謝料、財産分与などは夫婦関係調整調停(離婚)の際に、併せて話し合うことができます。
- ・DVや別居で、直接離婚の話し合いが出来ない場合も、調停を利用することで話し合いが可能です。

調停離婚の手続きと流れ |

家庭裁判所に調停を申し立てます。

- ・「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」に、「申立人」として、「夫婦関係調整調停(離婚調停)」の申立書を出します。
- ・調停離婚の理由は、法律で定められる原因でなくてもかまいません。
- ・親権者の指定や、養育費、財産分与、慰謝料などもの請求も離婚と合わせて行えます。
- ・すでに別居している場合、婚姻費用の分担を求める調停も、この時に一緒に申立ることができます。

調停開始
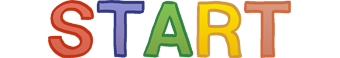
申立書が受理されてから約1ヶ月で調停が始まります。

調停

- ・男女1名ずつの調停委員に、夫婦が別々に意見を述べます(代理人がついていれば、夫婦は原則として顔を合わせることはありません)。
- ・まず夫婦関係の修復が可能かどうか図り、不可能だとなると、離婚の方向で調停が進められます。
- ・1ヶ月~2ヶ月に1回程のペースで数回開かれます。ほとんどが6ヶ月以内で終わりますが、それ以上かかる場合もあります。
- ・相手方が調停に出て来ない場合、出頭勧告してもらえる場合があります。
<相談のタイミング>
調停は、調停委員を交えての話し合いの場なので、自分の意見がうまく伝えられないことがありますので、調停が始まる前に弁護士にご相談ください。そうすることで戦略的に、離婚調停を有利に進めることができます。調停には原則として付添人は認められませんが、弁護士は代理人として同行が認められています。

調停成立
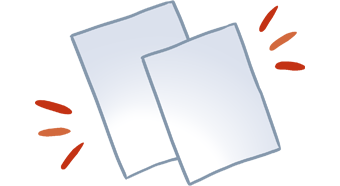
- ・二人の離婚の気持が固まり、親権者や養育費、財産分与や慰謝料などの離婚条件についても合意できれば、調停離婚が成立します。
- ・調停で合意した内容は調停調書が作成されます。
- ・「調停調書」は、確定判決と同じ効力を持ち、後で不服を申し立てることはできません(※親権や養育費など将来の生活おいて事情が変われば変更申し立てをすることは可能)から、書類作成時にしっかり確認しましょう。
- ・「調停調書」に記載された金銭支払いが、万が一滞った場合、すぐに強制執行(給料や財産の差押え)ができます。
- ・離婚届は、一方当事者が調停成立から10日以内に、離婚届に調停調書の謄本、戸籍謄本(本籍地でない役所に出す場合)を添えて、市町村役場に提出します。離婚届に双方の押印は必要ではなく、戸籍の変更当事者が単独で行います。一方当事者が提出しなければ、成立の10日以降、相手方から提出できます。
- どちらが離婚届を提出するかは、調停の時に裁判所に決めてもらえます。

調停不成立

どうしても話し合いで解決できる見込みがないと判断されると、調停不成立ということで、離婚が成立しないまま調停は終了します。調停不成立に対して、不服の申立はできません。
申立人は途中で調停を取り下げることができ、相手方の同意や理由は必要ありません。
第三者が入ることで、当事者だけより話が進展しやすく、相手方と直接顔を合わせずにすむので、安心して自分の意見が言え、不当・不公平な離婚を避けられます。
親権、養育費、面会交流権、慰謝料、財産分与等の離婚条件についても話し合えます。
調停で合意した内容は、裁判所が調停調書として作成します。
二人が合意しなければ調停での離婚は成立しません。
離婚問題に関する解説
「離婚の手続き」に関する一覧

-
みお綜合法律事務所 大阪事務所 /
JR「大阪」駅直結〒530-8501
大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
-
みお綜合法律事務所 京都駅前事務所 /
JR「京都」駅から徒歩2分〒600-8216
京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階(京都ヨドバシすぐ近く)TEL. 075-353-9901 FAX. 075-353-9911
-
みお綜合法律事務所 神戸支店 /
阪急「神戸三宮」駅から徒歩すぐ〒651-0086
兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階(神戸国際会館すぐ近く)TEL. 078-242-3041 FAX. 078-242-3042
![~ 新たな一歩を踏み出すための離婚問題解決サイト ~ Re-Start[リスタート]](/img/common/logo2.png)